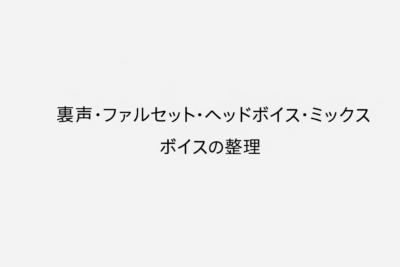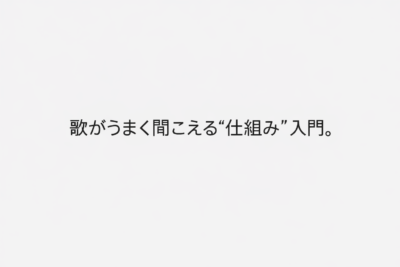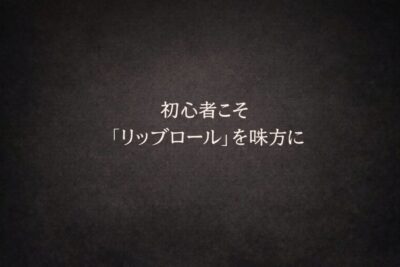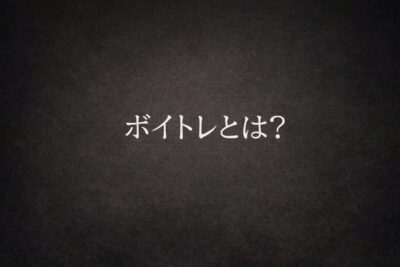第1回 ボイストレーニング 見えない楽器を知る ― 声帯と発声の基本構造
カテゴリ
歌を学び始めたとき、誰もが「もっと高音を出したい」「声量を増やしたい」と希望します。しかし、ただ練習量を積んでも結果が出ない場合が多いのはなぜでしょうか。
その理由の一つは、自分が扱う楽器――つまり「発声の仕組み」を知らないまま、感覚だけで声を出しているからです。
ピアニストが鍵盤やペダルの働きを理解せずに練習しないように、歌い手にとっても「見えない楽器」を理解することが欠かせません。本稿では、声がどのようにして生まれるのか、そしてその知識をどのように練習に活かせるのかを解説します。
喉のランドマークを触れて確かめる
まずは声帯の位置を把握しましょう。顎の下から指をなぞると、小さな骨の出っ張りが見つかります。これが「舌骨」です。さらに下に移動すると、男性では特に目立つ「甲状軟骨」、いわゆる喉仏に触れます。その下には「輪状軟骨」があります。これらは声帯を守るフレームのような役割を果たしています。
声帯そのものは甲状軟骨の奥に水平に張られており、長さは約1.0~2.0センチ、厚みはわずか数ミリ。筋肉と粘膜でできた柔らかな組織です。わずかこの小さな膜の振動が、私たちの歌声のすべてを生み出しているのです。
声の誕生とベルヌーイ効果
声帯がどのように振動し、音を生むのかを理解するには「ベルヌーイの法則」が欠かせません。肺から押し出された空気が声帯の隙間を通過すると圧力が下がり、声帯は吸い寄せられるように閉じます。次の瞬間には空気の力で押し広げられ、再び閉じる。この開閉が高速で繰り返されることによって振動が生じ、音源が生まれます。
たとえばA(ラ)の音を出すとき、声帯は1秒間に440回も開閉します。歌唱とは、肉眼では確認できない精密な物理現象を体内で行っている行為なのです。
地声と裏声、そのあいだ
発声の種類を大きく分けると「地声(チェストボイス)」と「裏声(ヘッドボイス)」に分類されます。地声は声帯全体が厚く接触して振動し、力強く芯のある響きを生みます。裏声は声帯の粘膜部分だけが薄く震え、透明感のある音色になります。さらに息漏れを伴うと「ファルセット」と呼ばれ、囁きに近い響きになります。
大切なのは、この二つ(地声と裏声)が単純な二項対立ではないという点です。声帯の閉じ方は連続的に変化しており、厚い閉鎖から薄い閉鎖までのグラデーションが存在します。プロの歌手はこのグラデーションを自在に操り、ジャンルや曲調に応じて音色を調整しているのです。
実感できる練習法
・喉の地図を描く
鏡の前で、舌骨→甲状軟骨→輪状軟骨を順に触れて位置を確認します。発声前にこの「喉の地図」を意識することで、声帯がどこにあるかを実感できます。
・紙でベルヌーイ効果を体験
A4の紙を二枚用意し、口の前に垂らします。下から息を吹きかけると紙が内側に吸い寄せられるように動きます。声帯でも同じ現象が起きていると理解でき、息と声の関係を体感できます。
・地声・裏声・囁き声を録音して比較
同じ高さで「アー」と発声し、地声→裏声→囁き声の順に録音します。その違いを聴き比べることで、声帯の閉鎖度が音色にどう影響するかを客観的に確認できます。
まとめ
声は「見えない楽器」です。
その構造を理解することは、単なる知識の習得ではなく、自分の発声を正しく認識するための手がかりです。声帯の仕組みを知り、ベルヌーイ効果を体験し、地声と裏声のグラデーションを意識する。これらの理解が、今後の歌唱トレーニングの確かな基盤になります。
次回は、この声帯の「厚み」と「薄さ」をどう操り、歌声を自在にデザインしていくかを詳しく探ります。
第2回 ボイストレーニング 歌声をデザインする ― 厚みと薄さのコントロール
第3回 ボイストレーニング アーティストに学ぶ ― Adoの歌唱分析
第4回 ボイストレーニング 表現力の完成 ― 声と感情のリンク~ミュージカル視点でみると・・・
カテゴリ