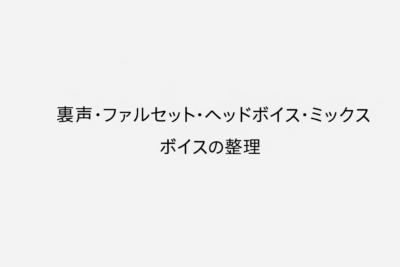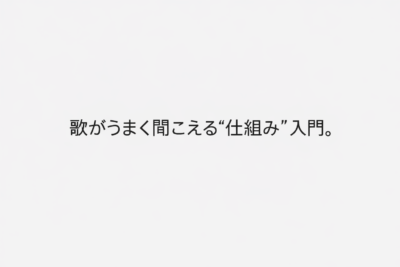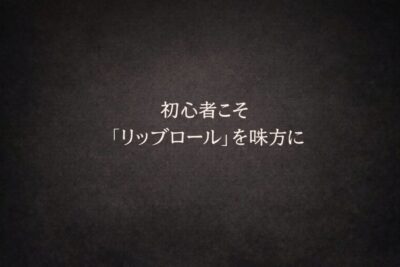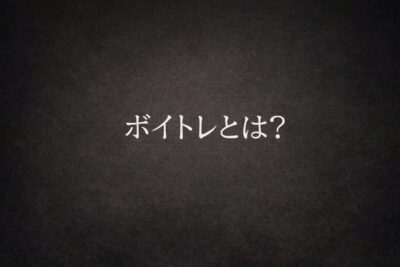第1回 英語の「音」を掴む ― フォニックスの基本と母音・子音の壁
カテゴリ
洋楽を歌ってみたい――。
そう思っても、「英語の歌詞って難しそう」「カタカナで書いても全然英語っぽく聞こえない」と感じたことはありませんか?
実はその感覚、とても自然です。英語と日本語は、音の仕組みが根本的に違うからです。日本語は「あ・い・う・え・お」という母音を中心にした“安定した音”の言語です。一方、英語は「息を遮ってから出す子音」と「口の形や舌の位置で変化する母音」の組み合わせで成り立っています。つまり、英語は“息と筋肉で作る音の言語”。カタカナに直した時点で、もう英語のリズムやニュアンスから離れてしまうのです。
■フォニックスとは何か
英語の発音学習で重要なのが フォニックス(Phonics)。
これは、アルファベットの「文字の名前」と「実際発音する音」を結びつけて覚える方法です。たとえば “C” は「シー」ではなく、音としては「クッ」。“A” は「エー」ではなく「あ」と「え」の中間――このズレを身体で理解していくのがフォニックスです。
日本語の「あ」は常に同じ音ですが、英語の “a” は単語によってまるで別人になります。cat の “a” は「ア」と「エ」の中間、cake の “a” は長く伸ばす「エイ」。アルファベットと発音が一致しないのが英語の特徴であり、逆にこの法則を知ると、「知らない単語でも発音の見当がつく」という効果があります。
英語圏の子どもたちは、このフォニックスを幼少期から学び、音と文字をセットで覚えます。それが“発音できる=聞き取れる”英語耳を育てる理由です。
■母音と子音 ― “息の流れ”を感じよう
英語の子音(consonant)は 息の流れを一度止めてから出す音 です。
たとえば “B” は唇で息を止めて破裂させる音。
“F” は下唇と上の歯で息を摩擦させる音。
“R” や “L” は舌の位置で響き方が変わり、日本人が最も苦手とする部分です。この「息の通り道をコントロールする感覚」を掴むことが、英語発音の第一歩。つまり、呼吸のコントロール=発音のコントロール なのです。歌のトレーニングとしても、フォニックスはまさに“発声筋トレ”。声を出す位置、舌の使い方、息のスピードがすべて音に影響します。
■「曖昧母音」シュワーの存在
さらに英語には、日本語にない「曖昧母音(schwa)」という音があります。これは単語の中で力を抜いて発音する、あいまいな母音。たとえば “banana” は「バナナ」ではなく “bəˈnænə”。真ん中の “næ” にアクセントがあり、他の母音は軽くぼかされています。この“ぼかす感覚”が、リズムを自然に流す鍵になります。
すべての音を正確に発音しようとすると、リズムが重くなり、カタカナ調になってしまうのです。面白いことに、この曖昧母音の感覚は、日本語の歌唱にも応用できます。母音をきっちり出しすぎると、フレーズが固くなりがち。逆に少し力を抜いて転がすように発音すると、メロディが流れ出します。つまり、「曖昧にする」ことでリズムが生まれる。これが英語発音の奥深さであり、歌の表現力を広げる鍵でもあります。
■カタカナ英語を卒業するには
洋楽を“カタカナ英語”で歌っていると、自分でも「ダサい」と感じる瞬間があります。それは単に発音の問題ではなく、息と筋肉の使い方が日本語のままだからです。「カタカナで書いて歌う=母音で終わる音になる」ため、英語特有の締まりや抜け感が失われます。
まずはカタカナを見ないで、英語のまま音を聴く。音源や動画を“シャワーのように浴びて”音の流れを身体に入れることが大切です。最初は聞き取れなくても構いません。フォニックスを通じて、「あ、この単語のaはこう響く」「このtは落ちている」と気づけるようになると、耳と口が少しずつつながっていきます。
英語を「読む」よりも「聴く」から始める――それが、洋楽を歌うための第一歩なのです。
カテゴリ