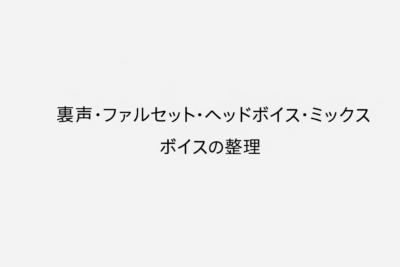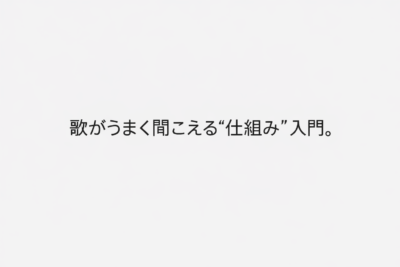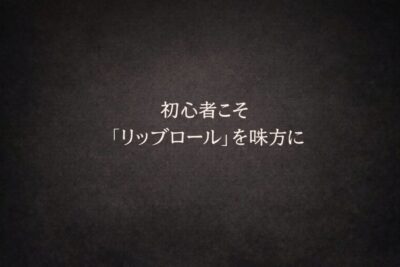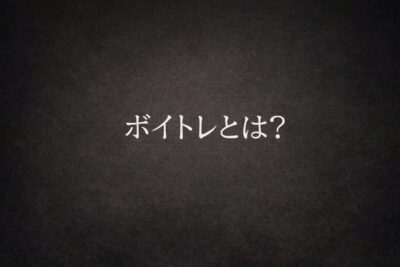第2回 英語発音の筋トレ ― 舌と唇がつくる音の表情
カテゴリ
英語の歌を歌うとき、「同じフレーズなのにネイティブが歌うと全然違う」と感じたことはありませんか?
それは声帯や口腔だけでなく、舌・唇・歯・顎といった“アーティキュレーター(調音器官)”の使い方が根本的に異なるからです。
英語は、音そのものが筋肉運動の結果として生まれます。つまり「英語の発音練習=発声筋トレ」。洋楽を自然に歌うためには、この筋肉の感覚を覚えることが欠かせません。
■1. 破裂音(Plosive)― 息を止めて爆発させる
英語では、「息を一度止めて破裂させる」音が多く存在します。
代表的なのは B・P・T・D・K・G です。たとえば “bag” は、「バッグ」ではなく 息の破裂を感じる bag(バグ)。唇を閉じて一瞬息をため、「ブッ」と弾くイメージです。P の場合はさらに無声音なので、声帯を鳴らさず 空気の圧だけでパッと放つ。紙を口の前に置いて、破裂音でふわっと動けばOK。
日本語ではほとんど使わないこの破裂感が、英語のリズム感を作ります。歌唱でも、言葉の立ち上がりを鋭くすることでグルーヴが生まれるのです。「音を押し出す」のではなく、「息を解放する」意識を持つと自然な発音に近づきます。
■2. 摩擦音(Fricative)― 息をすり合わせて響かせる
次に、息を擦り合わせる音=摩擦音。代表は F・V・S・Z・TH(θ/ð)・SH など。F は下唇を軽く噛んで「息をこすらせる」音です。このとき、強く噛みすぎると声が詰まるので、「唇に軽く歯を置いて、息を抜く」くらいがちょうどよいバランス。
摩擦が“鳴る”ことよりも、“流れる”ことが大事です。F と V の違いは、声帯を鳴らすかどうか。F は無声音(息だけ)、V は有声音(声をのせる)です。
つまり、声が震えていればV。この感覚を身につけると、“very” や “victory” の響きがぐっと立体的になります。
■3. LとR ― 日本人の永遠の課題
L と R の違いは、舌の動きと口の中の共鳴空間にあります。L は 舌先を上の歯茎に軽く当てて、舌の両側から息を抜く音。R は 舌先をどこにも触れさせず、やや奥にカールさせて口腔の奥を響かせる音。どちらも「舌の先がどこにあるか」で決まります。
L は「触れる」、R は「触れない」。この違いを意識して “light” と “right” を練習してみましょう。日本語ではどちらも「ライト」になりますが、英語では舌の動きが異なるため、音色の表情がまったく変わるのです。舌の筋肉が硬い人は、ストレッチから始めるのがおすすめ。
舌先を唇の内側で円を描くように回したり、「らりるれろ」をゆっくり発音して舌の可動域を広げる練習も効果的です。
■4. 有声音と無声音のバランスを意識する
英語の子音は、声を伴う「有声音」と、息だけの「無声音」に分かれます。日本語ではこの差が小さいため、どちらも同じように発音してしまいがちです。しかし、歌においてはこの違いがリズムに直結します。
たとえば “bad” と “pat”。
両方とも母音は同じですが、前の子音が有声(b)か無声(p)かでまったく印象が異なります。英語の歌では、息の流れを止めるか、流すか が表現の鍵。この感覚を持つだけで、歌詞のニュアンスが一気に豊かになります。
■5. 発音図鑑アプリで「見て」学ぶ
「発音図鑑」アプリを使用し、舌や口の動きを視覚的に確認できる教材はとても有効です。
実際に口内の断面図がアニメーションで表示され、息の流れが水色で動くなど、音の正体を“見える化”してくれます。発音は耳だけではなく、身体感覚と視覚で覚えるのがコツ。
「自分がどう動かしているか」を客観的に見られると、無意識の癖を修正しやすくなります。ボーカルトレーニングでも、鏡を見ながら口の形や舌の動きを観察すると効果的です。
■6. 歌唱への応用 ― 子音を「立てる」意識
英語の発音練習をボーカルに生かすには、「母音で歌う」から「子音を立てて歌う」への発想転換が必要です。日本語では母音がメインですが、英語では子音がリズムを刻みます。
特にミュージカル曲や洋楽バラードでは、破裂音でリズムを出し、摩擦音で流れを作ることが重要。歌詞や台詞を聞き取りやすく発音する効果もあります。日本語の滑らかさを保ちつつ、子音でビートを感じる練習をしてみましょう。
おすすめは、短いフレーズを 子音だけで歌う 方法。“Let it be” を「L-t-b」とリズムで唱えるだけでも、音の立ち上がりやタイミングが自然に整っていきます。
■7. 「筋肉で覚える英語」からリズムへ
フォニックスで“音の仕組み”を理解し、今回のように“筋肉で発音を覚える”ことで、英語の歌が身体に入ってきます。
英語は文法でなく呼吸とタイミングが大切。音を筋肉で感じられるようになると、意味を追うよりも先に、リズムの中で自然に発音が流れていくのを実感できるはずです。
カテゴリ