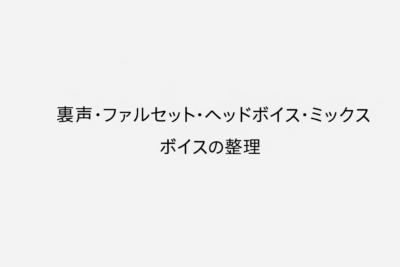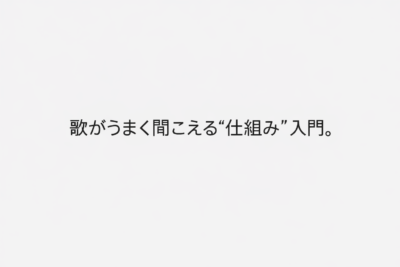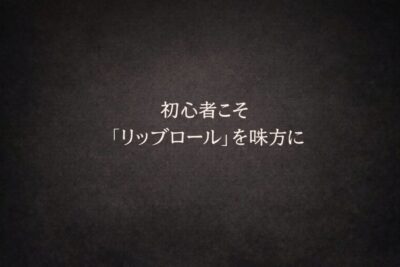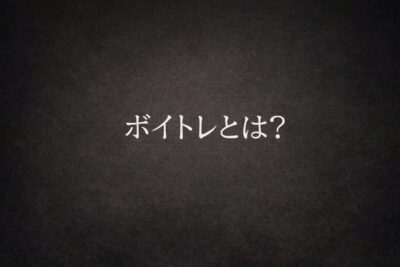第3回:アニソン・ボカロを歌いこなすための実践練習法
カテゴリ
はじめに
アニソンやボーカロイド曲を歌いたい!と教室を訪れる生徒さんは年々増えています。しかし実際に取り組んでみると「テンポが速すぎて歌えない」「高音が続いて喉がつらい」「機械的なフレーズを人間らしく再現できない」といった壁にぶつかります。ここでは、ボイストレーナー研修で取り上げられた内容をもとに、実際に役立つ練習法を紹介します。
① リズムを正確に刻む ― 打ち込みを活用する
アニソンやボカロ曲の大きな特徴は、テンポが速く細かいリズムが多いこと。
「春を告げる」や「Adoの『踊』」のような曲を歌うとき、まずはリズムの土台を体で感じることが重要です。
- 練習法
- DAW(Cubaseなど)で ドラムだけを打ち込む。特に「4つ打ち」やハイハットの16分刻みを繰り返し流す。(メトロノームアプリなどでも代用可能)
- その上で、歌詞を外して「ラ」や「タ」で歌ってみる。
- 歌詞の子音を後から乗せることで、テンポに振り回されずに歌えるようになる。
打ち込みは「メトロノームよりも実際の曲に近いリズム感」を体に入れるのに有効です。
② 高音対策 ― キー調整
ボカロ曲は人間にとって無理のある高音域が連続することも少なくありません。
- 練習法
- キーを半音〜全音下げた音源を用意:Cubaseで簡単に移調可能。無理なく歌える高さで練習する。(最新のアプリでも容易にキー調整ができるものがあります)
- 段階的に原曲キーに戻す:徐々に喉に負担をかけずに慣れていく。
- 発声練習で高音ウォームアップ:「リップロール」などを取り入れて、声帯をスムーズに伸展させる。
高音が楽に出せるようになると、曲全体の表現にも余裕が生まれます。
③ 表現力 ― 「機械的な歌」を人間らしくする
ボカロ曲の特徴は、機械的で正確な歌唱。人間がそのまま真似すると「棒歌い」になりがちです。
そこで必要なのが「人間らしいニュアンス付け」です。
- 練習法
- ベロシティ調整をイメージ:打ち込みで音の強弱(ベロシティ)を変えるように、自分の声でも強弱をつける。
- タイミングをずらす:あえて機械的なジャストではなく、コンマ数秒遅らせたり先取りすることで感情が出る。
これにより、機械的な楽曲を「人が歌う意味のある表現」へと昇華できます
④ カラオケ練習とガイドメロ活用
Cubaseや最近のDAW、アプリなどには「ボーカル抽出」「オケと歌の分離」機能が搭載されています。これを利用すると、自宅練習用の教材がすぐに作れます。
- ボーカル抽出 → MIDI化:録音した歌声を解析し、MIDIデータに変換。ガイドメロディを作って音程確認に使える。
- カラオケ音源作成:オケだけを取り出して練習。自分の声を録音して比較できる。
⑤ 教材としてのアニソン・ボカロ
ボイストレーナー視点では、アニソン・ボカロ曲は単なる「流行の歌」ではなく、教材として極めて優秀です。
- リズム感トレーニング:高速テンポ・複雑なリズムを体得できる
- 音域拡張:高音域の挑戦が自然に取り入れられる
- 表現力育成:機械的フレーズに人間らしさを加える練習ができる
おわりに
ここまで3回にわたり、DTM・ボーカロイド・アニソンの仕組みと歌唱練習法を解説してきました。音楽制作の技術と歌のレッスンは、これまで別物と考えられてきましたが、実は密接に結びついています。パソコンを楽器のように扱い、ボカロ曲を教材として使うことで、歌の学びはさらに面白く、実践的になります。
これから挑戦したい方は、ぜひ自分の好きなアニソンやボカロ曲を題材に、今日から一歩踏み出してみてください。
カテゴリ