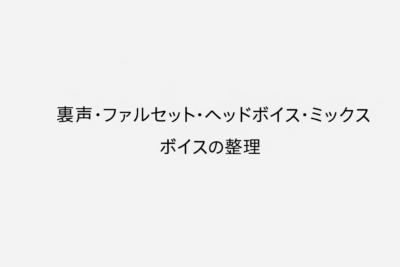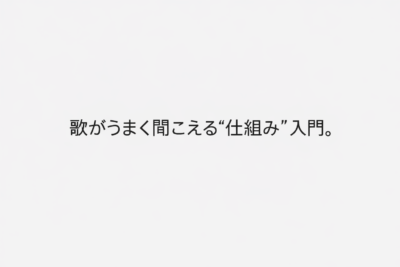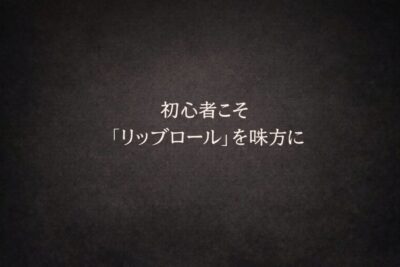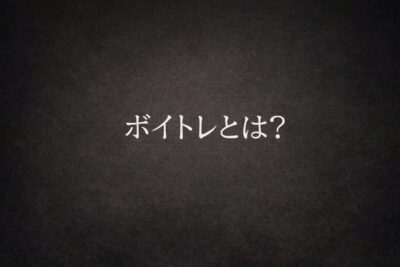第2回 ボイストレーニング 歌声をデザインする ― 厚みと薄さのコントロール
カテゴリ
歌声の個性や印象を決定づける最大の要素のひとつが「声帯接触の厚みと薄さ」です。高音を楽に出したいと願う人も、低音に安定感を求める人も、この「厚さと薄さ」を理解しなければ上達は望めません。同じ音程であっても声帯を厚く使うか薄く使うかによって、響きはまったく異なるものになります。
ここでは、日常的な会話の延長から専門的なトレーニングまで、厚みと薄さのコントロールを具体的に考えていきます。
厚い接触 ― 力強さと存在感
「おはようございます」と低めの声でやや強めに言ってみると、胸に響く振動を感じるでしょう。これは声帯が厚く閉じ、接触面積を広く使っている状態です。接触が厚いほど声は密度を増し、マイクを通さずとも会場に届く力強さが生まれます。ロックやソウル、演歌など、感情を直接的に伝えるジャンルでは必須の響きです。
厚い接触は力感を出す一方で、無理に押し出すと声帯に負担がかかります。重要なのは「厚みを持たせても柔軟さを失わない」こと。筋肉的な圧迫ではなく、息の流れと声帯閉鎖のバランスを取ることがポイントです。
薄い接触 ― 透明感と伸び
同じ「おはようございます」を、今度は軽やかに、鼻腔に抜けるような響きで言ってみましょう。すると声が軽く明るくなり、透明感が増すのを実感できるはずです。これは声帯が薄く接触している状態で、クラシックやミュージカルの発声に代表されます。
薄い声帯接触のメリットは、息の流れが豊かに保たれます。るため、響きがホールの奥までスムーズに届くこと。声が「抜ける」と表現されるのはこの状態です。ただし薄すぎると力感が失われ、頼りない印象を与えてしまうため、どの程度まで薄くするかのコントロールが重要です。
囁き声との関係
囁き声は声帯の接触をすくなくした、または、ほぼ接触がない状態で をほぼ開放した状態で、息だけで音を作る方法です。直接的な歌唱では使われませんが、「声帯を閉じる/開く」という感覚を把握するうえで有効です。囁きから薄い声へ、さらに厚い声へと段階的に変化させると、接触度合いがどのように変わるのかを感覚的に理解できます。
音楽的な使い分け
バラードではAメロを薄く柔らかく始め、サビで厚く力強く歌うことでメリハリがつきます。逆にロックでは、Aメロから厚めに声を乗せて緊張感を高め、サビで一気にシャウトに近づける手法も有効です。厚みと薄さは単なるテクニックではなく、音楽のドラマを描くための色彩です。
練習法
- 「おはよう」二重唱
同じ音程で「おはよう」を厚い声・薄い声で繰り返し、違いを録音して確認します。 - 囁きから薄い声へ
囁き声で「アー」と発し、息を保ったまま声帯を閉じて薄い声に移行します。息と閉鎖の境界を体感できます。 - ピアノを使った交互発声
ピアノで中音域を弾き、厚い声→薄い声→厚い声と切り替えて歌います。音程を変えて練習することで幅広い音域に応用可能です。
まとめ
声帯接触の厚みと薄さは、歌声の印象を決定づける「設計図」です。厚さで力を訴えるか、薄さで透明感を伝えるか。その選択は、曲の解釈そのものに直結します。次回は、この技術をアーティスト――Adoの歌唱分析を通してさらに深めていきます。
第1回 ボイストレーニング 見えない楽器を知る ― 声帯と発声の基本構造
第3回 ボイストレーニング アーティストに学ぶ ― Adoの歌唱分析
第4回 ボイストレーニング 表現力の完成 ― 声と感情のリンク~ミュージカル視点でみると・・・
カテゴリ