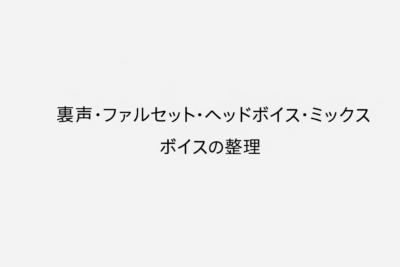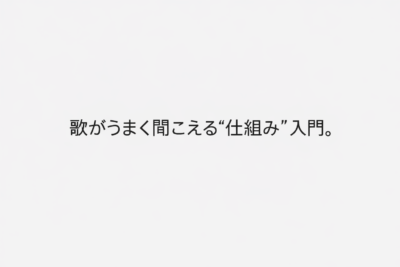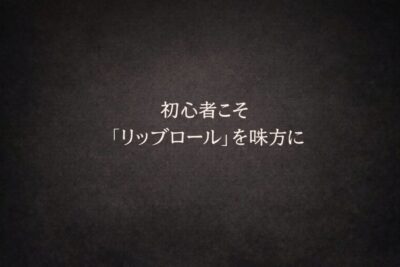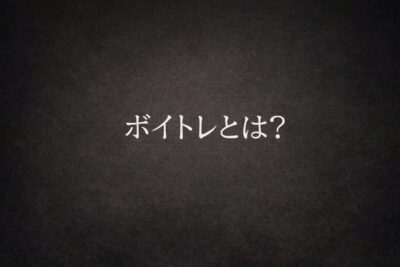第2回:倍音とハーモニー ― 声の響きが合うとはどういうことか~歌に役立つオンライン講座~
カテゴリ
歌を習い始めると、「音程は合っているのに、なぜかハモって聞こえない」という不思議な体験をする方が多いと思います。実はその理由は「倍音」にあります。
今回は、歌声や楽器の響きに欠かせない倍音の仕組みと、ハーモニーとの関係を掘り下げていきましょう。
倍音とは何か?
私たちが耳にしている音は、決して一つの周波数だけでできているわけではありません。
例えばピアノで「ド」の音を弾いたとしましょう。基音となる「ド」の周波数(C4=約262Hz)に加えて、その2倍、3倍、4倍…という周波数が同時に鳴っています。これが倍音です。
• 基音:262Hz(C4)
• 第1倍音:524Hz(C5、1オクターブ上のド)
• 第2倍音:786Hz(G5、ソの音)
• 第3倍音:1048Hz(C6、さらに1オクターブ上のド)
このように、1つの音の中には複数の周波数が含まれており、それが音色の正体となっています。ピアノ、ギター、フルート、そして人の声が同じ高さの音を出しても違って聞こえるのは、この倍音の含まれ方が異なるからなのです。
倍音がつくる「音色」
音色とは、楽器や声の個性を決める重要な要素です。
例えば、同じ「ラ」の音でも、バイオリンは鋭く澄んだ音に、フルートは柔らかく温かみのある音に、人の声なら深みのある声や明るい声に聞こえます。その違いは、基音の上にどんな倍音がどれだけ含まれているかで決まります。
• 倍音が整っている → クリアで澄んだ音色
• 倍音が複雑に歪んでいる → 厚みや個性を持つ音色
歌声も同じで、母音の発声や声帯の厚みを変えるだけで倍音構成が変化します。だからこそ、ボーカルトレーニングでは「母音を揃える」ことや「響きを整える」ことが大切になるのです。
ピッチが合ってもハモらない理由
合唱やコーラスで「音程は正しいのに、きれいに揃って聞こえない」ことがあります。この原因も倍音にあります。
人それぞれ声帯の厚みや口腔の形が違うため、同じ音を出しても倍音の含まれ方が異なります。その結果、基音(ピッチ)が合っていても、上に重なる倍音同士がずれてしまい、響きが濁ってしまうのです。逆に、倍音が似ている声同士が集まると、まるで一人が歌っているかのように溶け合って聞こえます。これが「声がそろう」という状態です。
合唱やコーラスでの工夫
プロの合唱団やアンサンブルでは、倍音を揃えるためにいくつかの工夫が行われています。
1. 母音を統一する
「あ」や「い」といった母音は、口の開き方で倍音構成が大きく変わります。全員で同じ母音の形を意識することで、音色がまとまりやすくなります。
2. 声帯の厚みをそろえる
声帯を強く閉じて厚い響きを出すのか、軽く薄くして明るい響きを出すのか。方向性をそろえることで、倍音が整いやすくなります。
3. 共鳴の位置を合わせる
鼻腔、口腔など、どこに響きを集めるかをそろえると、声の方向性が一致して一体感が生まれます。
これらは単なる音程練習ではなく、響きそのものを意識した高度なトレーニングといえるでしょう。
倍音を意識した実践トレーニング
自宅でもできる、倍音を感じる練習をいくつか紹介します。
• 母音チェンジ練習
同じ音程で「あ→い→う→え→お」と母音を変え、響きがどう変化するかを観察する。
• ハミング練習
鼻腔に響きを集めるように軽く口を閉じて声を出す。
• ユニゾン練習
誰かと同じメロディーを歌い、音程だけでなく響きがそろう感覚を探る。
こうした練習を繰り返すと、耳が倍音に敏感になり、コーラスやハーモニーの中で自分の声をどうコントロールすればいいかが見えてきます。
倍音をそろえることの意味
「倍音をそろえる」と聞くと、個性が消えてしまうように感じるかもしれません。しかし実際は逆です。基礎として倍音を整えた上で、自分なりに崩したり歪ませたりすることで、初めて“表現”が生まれます。
クラシックの合唱では極限まで倍音をそろえて純度の高い響きを追求しますが、ジャズやゴスペルではあえて倍音がぶつかり合うことでパワフルなサウンドを生み出します。どちらが良い悪いではなく、ジャンルや表現に応じて響きを選ぶことが大切なのです。
まとめ
• 音には基音のほかに倍音が含まれており、それが音色を決める
• ピッチが合っていても倍音がずれるとハーモニーは濁る
• 合唱では母音や声帯の厚み、共鳴の位置をそろえることで倍音が整う
• 倍音を意識した練習を通じて、声を「そろえる」「個性を出す」の両方が可能になる
歌は単に正しい高さの音を出すだけではなく、「響きをデザインする芸術」です。倍音という視点を持つことで、これまで以上にハーモニーの世界を楽しめるはずです。
次回は、さらに踏み込んで「声帯の仕組みとピッチコントロール」について解説します。声帯がどのように動くことで音が変わるのかを理解すると、歌声の可能性がぐっと広がります。
第3回:声帯の仕組みとピッチコントロール ― 自分の楽器を知る
カテゴリ