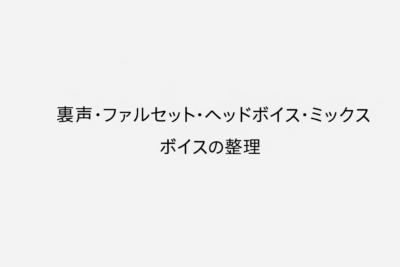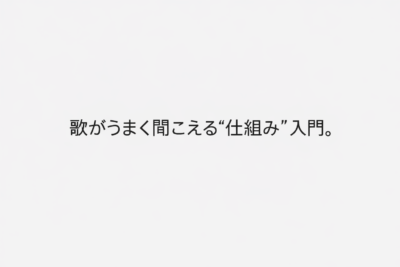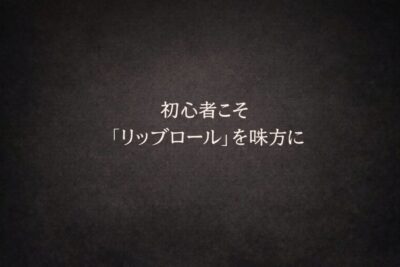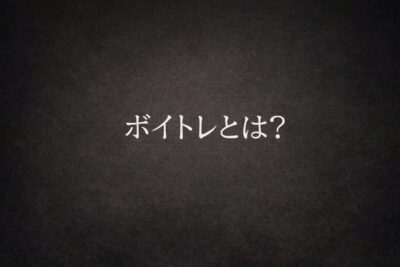第1回:ピッチとは何か? ― 音の高さと人間の耳の不思議~歌に役立つオンライン講座~
カテゴリ
歌の練習を始めたばかりの頃、多くの方が「ピッチが悪い」「音程がズレている」と指摘されて戸惑います。正しく歌っているつもりなのに、なぜか「低い」と言われてしまう…。今回は、この「ピッチ」という概念を深く掘り下げて解説していきます。
ピッチとは「振動数」
ピッチとは「音の高さを決める振動数」のことです。
楽器や声は、空気を振動させて音を生み出しています。例えば、ピアノの「ラ」の音は 440Hz。これは 1秒間に440回の振動 を意味します。数字が大きいほど音は高く、数字が小さいほど音は低くなります。つまり、私たちが「高い声」「低い声」と呼んでいるものは、声帯の振動回数の違いなのです。声帯が引き伸ばされて速く振動すれば高音に、緩んでゆっくり振動すれば低音になります。歌うという行為は、声帯を繊細にコントロールする作業でもあるわけです。
ピッチと音程の違い
次に混同されがちな「音程」との違いを整理しておきましょう。
• ピッチ … 今出している音の高さそのもの(例:440Hzの「ラ」)
• 音程 … ある音と別の音との距離感(例:ドからレ=長2度)
レッスン中に「音程が悪い」と言われる場合、それは「ドからミまでの距離が正しく取れていない」といったことを意味します。一方「ピッチが悪い」とは、「ラを出すべきところで実際にはラ♯やソ♯になっている」といった高さそのもののズレを指します。両者は密接に関わりますが、区別して理解しておくと練習が効率的になります。
自分では合っていると思うのにズレる理由
多くの人が経験するのが「自分では合っていると思ったのに、先生からはズレている」と指摘を受ける。実はこれ、人間の耳の仕組みに原因があります。
私たちは自分の声を、
1. 空気の振動(外耳から鼓膜へ届く音)
2. 骨を伝わる振動(骨伝導音)
の両方で聞いています。
骨を通して聞く音は、空気を通す音よりも速く伝わるため、高く感じられやすいのです。つまり、自分には高く聞こえているのに、外側では低く鳴っている というズレが起きてしまうのです。この仕組みを知るだけでも「なぜ自分はいつもズレると注意されるのか?」という長年の疑問が解ける方も多いでしょう。
録音して初めてわかる自分の声
自分の声を録音で聞くと「思っていた声と違う」と驚く経験をしたことはありませんか?
これはまさに骨伝導と空気振動の違いによるものです。録音機材は空気の振動だけを拾うため、私たちが日常的に“自分の声”として認識している骨伝導の響きが含まれていません。そのため「高い」「軽い」「薄い」など、普段感じている声とギャップが生まれるのです。
この違和感に慣れることが、ピッチを正しく取る第一歩となります。歌の練習を録音して確認するのは、単に復習のためではなく、自分の耳を客観的な音に合わせるための訓練でもあるのです。
ピッチがズレやすいケース
では、どんなときにピッチはズレやすいのでしょうか?
1. 落ち着いた練習時
緊張が少ない分、骨伝導の影響が強く、自分には合っていても外からは低く聞こえやすい。
2. 本番や人前での歌唱時
逆に緊張で喉が上がりすぎると、今度はピッチが高く上ずってしまう。
多くの場合、レッスンで「ピッチが悪い=低い」と言われるのは1つ目のパターンです。自分の耳にとっては正しくても、外からは低く聞こえる。このズレを補正するために、耳と感覚を鍛える必要があるのです。
耳を鍛えるための実践法
ここからは、自宅でもできる簡単な「耳トレ」を紹介します。
• 壁や机を叩いて耳をつける
物体を通して伝わる音が高く聞こえることを体感すると、骨伝導の性質が理解しやすい。
• 楽器と合わせる
ピアノやキーボードで「ラ=440Hz」を鳴らし、自分の声を重ねて一致させる練習をする。
• 録音して聴く
スマホやICレコーダーで歌を録音し、実際のピッチを確認する。
• 耳をふさいで声を出す
手で耳を軽く押さえて声を出すと、骨伝導の音が遮られ、外側の音に近い響きが聞こえる。
こうした方法は、単純なようでいて非常に効果的です。継続することで、自分の「内側の耳」と「外側の耳」を一致させる感覚が養われていきます。
ピッチを理解することが歌の楽しさにつながる
ピッチは、単なる「正しい音程を取るための技術」ではありません。自分の体を“楽器”として理解し、外の音と一致させることで、初めて音楽は他者と共有できるものになります。カラオケでの歌唱も、バンドや合唱でのハーモニーも、このピッチの理解なしには成り立ちません。
「なぜズレると言われるのか?」「どうして録音の声は違って聞こえるのか?」――そうした疑問の答えを知ることで、練習への意識は大きく変わるはずです。
次回は、さらに一歩踏み込んで「倍音とハーモニー」について解説します。同じ音を出しているはずなのに、なぜか揃って聞こえない。その不思議を“倍音”の観点から掘り下げていきましょう。
第2回:倍音とハーモニー ― 声の響きが合うとはどういうことか
第3回:声帯の仕組みとピッチコントロール ― 自分の楽器を知る
カテゴリ