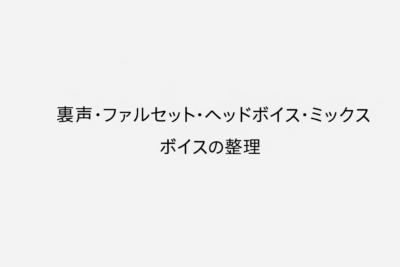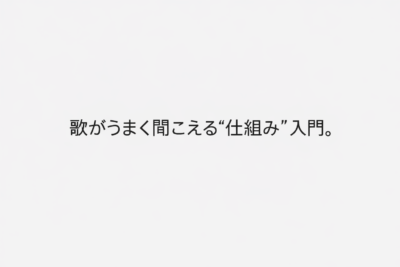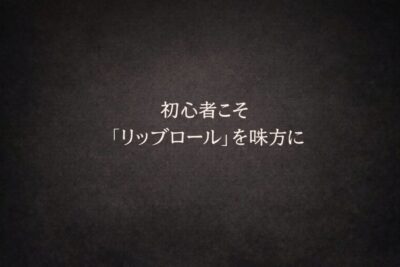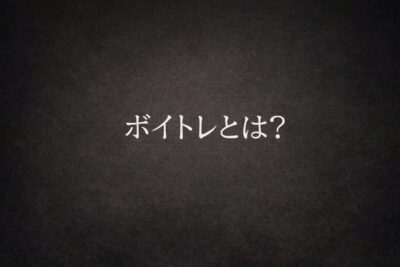リズム応用編 第2回~タイとアクセントの移動 ― 歌のノリを変える仕組み~
カテゴリ
「タイ」とは何か
リズムを応用的に学ぶ際に避けて通れないのがタイ(⌒)です。楽譜で隣り合う同じ高さの音符が曲線で繋がれている記号を見たことがあると思います。これは、二つの音符を「一つの長い音」として伸ばすことを意味します。
例えば、四分音符と四分音符がタイで繋がれていれば、それは二分音符と同じ長さになります。ただし、単に長くなるだけではなく、拍のアクセントの位置をずらす効果が生まれる点が重要です。音が伸びて次の拍の頭をまたぐことで、本来強く感じるはずの拍が「別の位置」に変わり、聴き手には新鮮なノリが伝わるのです。
アクセントの移動が生むグルーヴ
通常、4分の4拍子では「1拍目」と「3拍目」にアクセントを感じます。しかし、タイで音を繋ぐと、このアクセントが前後にずれます。
「アクセントがずれ込む」現象こそ、現代ポップスやR&Bのリズムの核心部分です。聴いているだけでは把握しにくいのですが、楽譜を読むとどの拍がつながっているかが一目瞭然になります。これが「譜面を読む力」が歌のノリに直結する理由なのです。
実際の楽曲に見るタイの効果
講座では、ある人気曲のAメロを題材に「符読み」を行いました。歌詞だけで覚えると、ロープを手繰り寄せるようにどこまでも流れていく感覚で、区切りが分からず混乱しがちです。しかし、譜面を見ると「ここでタイがある」「ここで付点がある」という情報が明確になり、作曲者の意図が理解できます。
実際に声に出してリズムを読んでみると、譜面のタイによって本来の拍からわずかに前にずれ込みます。すると、ただ真っ直ぐに歌った場合と比べて、言葉に勢いとノリが生まれるのです。これはまさに「譜面が作曲者からのメッセージ」であることを体感できる瞬間です。
ジャンルごとの違い
タイとアクセントのずれは、ジャンルごとにニュアンスが変わります。
• R&B … 前に食い込むリズムを強調することで粘り気のある歌い方になる
• ラテン音楽 … 拍の裏を感じることで、躍動感の強いグルーヴになる
• ミュージカルやクラシック … 記譜上の意図を忠実に守ることが求められ、歌詞とリズムの一致がドラマ性を生む
つまり、同じ「タイによるずれ」でも、どこを強調するかによってまったく異なる音楽的世界が立ち上がるのです。歌い手にとっては、単に譜面を読むのではなく、その曲が持つジャンル的背景を理解することが重要になります。
練習の進め方
1. 符読みの徹底
まずは音程を考えず、リズムだけを「タタタ」などで声に出して読みます
2. アクセントの確認
どの拍が伸び、どこにアクセントがずれ込むのかを意識しながら数えます
3. 歌詞をのせる
リズムの流れを理解した上で歌詞を当てはめると、自然とノリが生まれます
4. ジャンルを意識する
ポップスなら軽快に、R&Bなら粘りを持たせる、ラテンなら裏拍を意識するなど、リズムの“性格”を考えて練習すると効果的です
まとめ
今回扱った「タイ」は、リズムを単調にせず、楽曲に独特のグルーヴを与える重要な要素です。アクセントが移動することでノリが変化し、歌詞に説得力や表情が加わります。耳だけでは掴みにくいこの現象も、譜面を読むことで「なぜそのように聴こえるのか」が明確になります。
歌が「平板でかっこよくならない」と悩む人にとって、この理解は大きな転機となるでしょう。次回はさらに進んで、リズムとジャンルの関係性 ― R&B、ラテン、ミュージカルの比較を通じて、応用的なリズム解釈を深めていきます。
カテゴリ