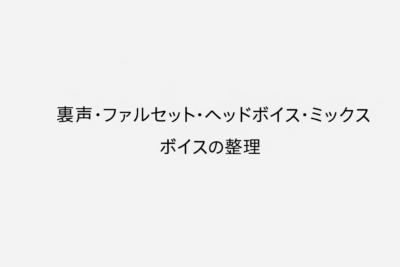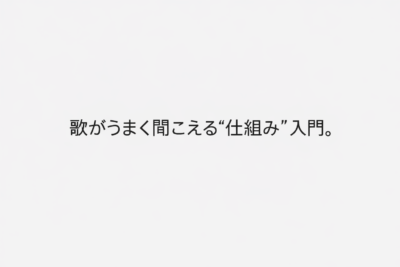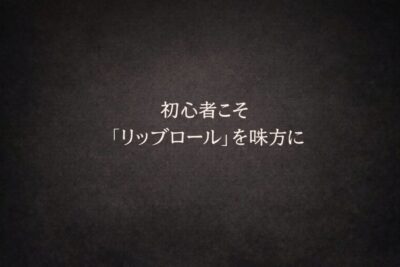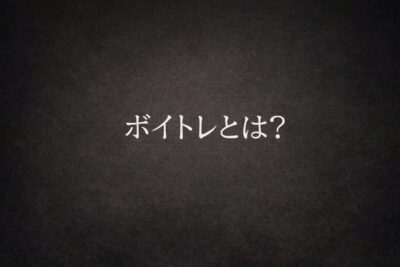第3回 ボイストレーニング アーティストに学ぶ ― Adoの歌唱分析
カテゴリ
ここ数年、日本のポップシーンで圧倒的な存在感を示してきたAdo。
10代でデビューし、瞬く間に国民的なアーティストとなった彼女の歌唱は、従来の「ポップスの常識」を覆すような多彩さとドラマ性を兼ね備えています。特に注目すべきは、声帯の厚みと薄さを瞬時に切り替え、音色を劇的に変化させる能力です。本稿ではAdoの歌唱を具体的に分析し、私たちが学べるポイントを探ります。
「うっせぇわ」に見る攻撃性とコントロール
Adoを一躍有名にした「うっせぇわ」では、冒頭から地声を厚く使い、強い閉鎖によって怒りや苛立ちを表現しています。特にサビの「うっせぇ うっせぇ うっせぇわ」のフレーズでは、子音を鋭く立て、声帯を厚く閉じて爆発的なエネルギーを生み出しています。
しかし、ただ叫んでいるわけではありません。言葉の最後には薄さを残して抜けを作り、音色に変化をつけています。この「押し出しと抜き」のコントロールこそが、単なるシャウトとの違いです。
「新時代」における多彩な切り替え
映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌「新時代」では、曲冒頭から薄い裏声で透明感を出し、サビに入ると厚い接触に切り替えて力強さを演出します。さらにブリッジ部分ではファルセットを織り交ぜ、息漏れを増やすことで儚さを表現しています。
わずか数分の楽曲の中で、Adoは地声・裏声・ファルセットを自在に行き来しています。しかもその切り替えは不自然さがなく、まるで演技のように音楽の流れに溶け込んでいるのです。
「私は最強」に見る劇的な展開
「私は最強」では、序盤を薄めの裏声で始め、少しずつ厚みを増してサビで爆発させます。後半にかけては地声の厚みを強調し、ラストに向かってディストーションボイスを織り交ぜることで劇的なクライマックスを築きます。
この「構成に合わせた厚さの設計」は、ミュージカルやオペラの手法にも通じます。Adoの歌唱が単なるポップスに収まらず、舞台的な迫力を持つのは、このダイナミックな設計力によるものです。
海外シンガーとの比較
Adoのスタイルは、アデルやビヨンセといったR&Bシンガーの「厚い声帯接触で力強さを出す」技術と、ブロードウェイ歌手の「薄い声での高音処理」を合わせたような多彩さを持っています。クラシックでは声色を大きく変えることは少ないですが、Adoはジャンルを横断しながら自在に切り替えている点が独特です。
つまり彼女は、日本語の歌詞にポップス的リズム感を乗せつつ、海外的な歌唱技術を取り入れて再構成しているのです。ここから私たちが学べるのは「一つの声に固執しない柔軟さ」です。
ディストーションとシャウトの安全な取り入れ方
Adoの歌唱のもう一つの特徴が、ディストーションやシャウトです。これは声帯上部にノイズを混ぜることで得られる音色です。間違った方法で練習すると声帯を痛める危険がありますが、正しく取り入れると大きな表現力を得られます。
まず薄く使って声を出し、そこに軽い圧迫を加えるとノイズが混じります。これを数秒だけ行い、喉に違和感がないかを確認します。長時間行わない、痛みを感じたら即中止する。このルールを守ることで安全に取り組めます。
練習法
- 一フレーズ分解
好きな曲のサビを取り出し、地声→裏声→ファルセットに分けて歌い分けます。録音して聴くことで、切り替えが自然に行えているか確認できます。 - 安全なディストーション導入
薄い声をベースに軽く圧迫を加え、ノイズを混ぜます。1日数分程度、短時間だけ練習しましょう。 - 歌詞マーキング
楽譜や歌詞カードに色ペンで「厚い」「薄い」「ファルセット」と書き込み、Adoがどこで切り替えているか分析します。自分で同じ箇所を試すと、切り替えの感覚が身につきます。 - 比較練習
Adoの楽曲と、クラシックやR&Bの楽曲を聴き比べ、それぞれがどのように厚みを使っているかを記録します。自分の歌に応用するヒントが得られます。
まとめ
Adoの歌唱は「声帯接触の切り替え」が生み出す表現の見本です。
「うっせぇわ」の攻撃性、「新時代」の多彩さ、「私は最強」の劇的展開。これらすべてが、厚みと薄さを自在に操ることで実現されています。彼女の歌を模倣する必要はありませんが、分析することで「自分の声にどんな可能性があるのか」を知ることができます。
歌声を一色に限定せず、場面ごとに塗り替える。その柔軟さを意識することが、表現力を磨くための第一歩となるはずです。
第1回 ボイストレーニング 見えない楽器を知る ― 声帯と発声の基本構造
第2回 ボイストレーニング 歌声をデザインする ― 厚みと薄さのコントロール
第3回 ボイストレーニング アーティストに学ぶ ― Adoの歌唱分析
第4回 ボイストレーニング 表現力の完成 ― 声と感情のリンク~ミュージカル視点でみると・・・
カテゴリ