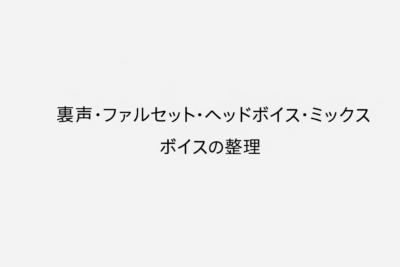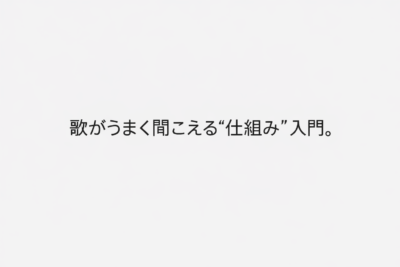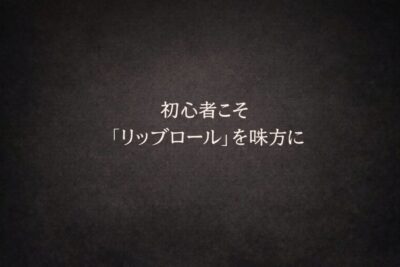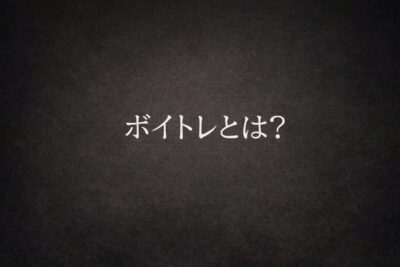キーボディストによる音源を聞き分ける講座 第5回~応用編 ― 曲をまるごと聴き分ける~
第5回:応用編 ― 曲をまるごと聴き分ける
ここまででドラム、ベース、ギター、鍵盤と、それぞれの役割を学んできました。
最後は「応用編」として、実際の楽曲を使いながら全体を聴き分ける練習をしてみましょう。
曲を聴き分けよう ― 実践編
レミオロメン『3月9日』とバウンディ『怪獣の花唄』
今回の講座では、具体的な楽曲を題材にして「音を聴き分ける」練習をしていきます。取り上げるのは、発表会でもよく選ばれる人気曲 レミオロメン『3月9日』 と、現代の代表的ヒット曲 バウンディ『怪獣の花唄』。同じ“バンドサウンド”でも、編成やアレンジの違いで聴こえ方が大きく変わります。
『3月9日』 ― シンプルだからこそ役割が見える
この曲は、ドラム・ベース・ギターというシンプルな編成が中心です。
• ドラム
キック(ドン)とスネア(パン)がリズムの骨格を作り、聴く人の体を自然に揺らします。
• ベース
ドラムと連動しながら、低音で曲を安定させています。ベースが入ると音楽全体が落ち着き、安心感を与えます。
• ギター
和音やアルペジオで彩りを添え、曲の雰囲気を豊かにします。
ピアノ伴奏に慣れている人は、「あれ、音がスカスカ?」と感じるかもしれません。でも実際には、ドラムとベースが基礎、ギターが彩りという役割に分かれているだけなのです。
🎧 練習のポイント
1. まずはドラムとベースだけを追いかけて聴いてみましょう。
2. そのうえで、ギターの和音やアルペジオに耳を移します。
3. 最後に全体を聴くと、「曲の骨組みと彩り」が見えてきます。
『怪獣の花唄』 ― 音のレイヤーを楽しむ
一方、『怪獣の花唄』は、音の層(レイヤー)がとても厚いのが特徴です。
• イントロからシンセサイザーが入り、曲全体を包み込むように響きます。
• サビに向かってギターやドラムが加わり、音の数が一気に増えていきます。
• オルガンやシンセの“背景の音”がふわっと重なり、曲に迫力と奥行きを与えます。
このように「どのタイミングで音が重なっているか」に耳を澄ませると、アレンジの工夫が見えてきます。
🎧 練習のポイント
1. まずはドラムとベースのリズムだけを聴きます。
2. 次に、シンセやオルガンの“背景の音”を探してみましょう。
3. 最後に全体を聴き直すと、音が立体的に重なっていることが実感できます。
まとめ
• 『3月9日』は シンプルな編成の中で役割を理解するのに最適。
• 『怪獣の花唄』は 音のレイヤーを聴き分ける耳を育てるのにぴったり。
ふだん何気なく聴いている音楽も、少し意識するだけで「ドラムとベースが支えている」「シンセが雰囲気を作っている」といった発見につながります。次に聴くときは、ぜひ楽器ごとに耳を動かしてみましょう!
ライブステージでの再発見
実際に発表会やライブで歌うと、練習のときには気づかなかった音が急に聴こえてくることがあります。「ここでシンセが重なってるから歌いやすいんだ」「このベースラインがあるから安心して歌えるんだ」――そうした気づきは、ステージ経験と耳の訓練が重なることで生まれます。
そして
音楽は「全員で作るもの」。
ドラムがリズムを刻み、ベースが支え、ギターや鍵盤が彩りを添える。歌はその上に乗って初めて輝きます。この応用編を通して、「ひとつの曲を分解しながら聴く」体験を積み重ねてみてください。きっと普段聴いている音楽が、今までより立体的に、そして豊かに感じられるはずです。